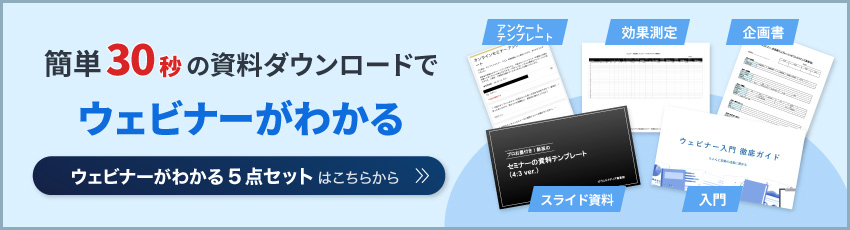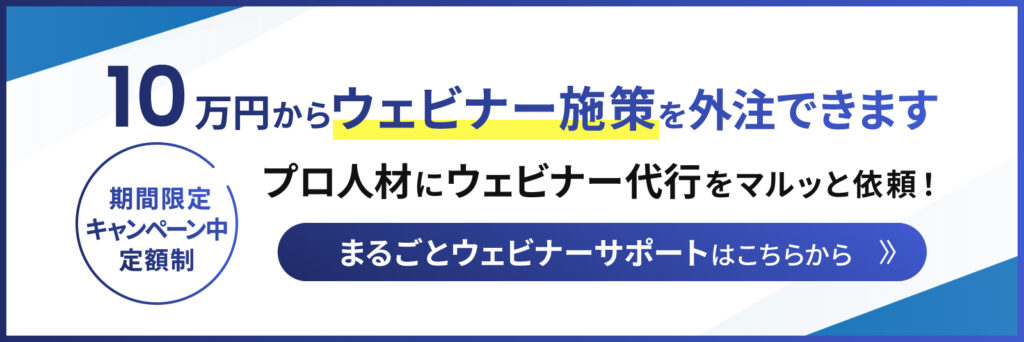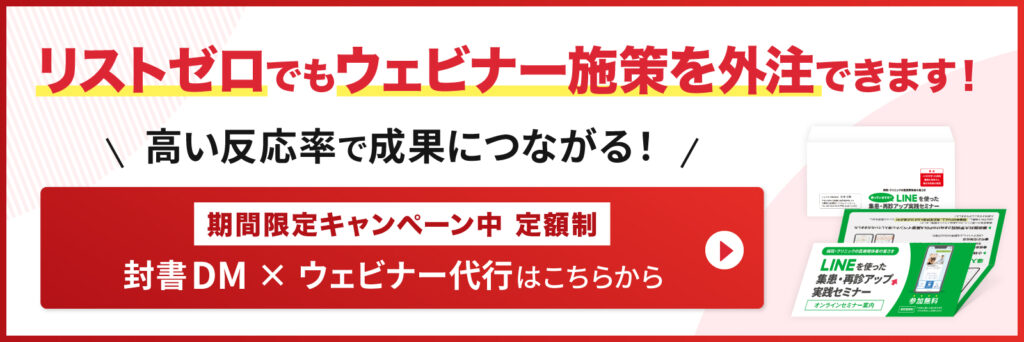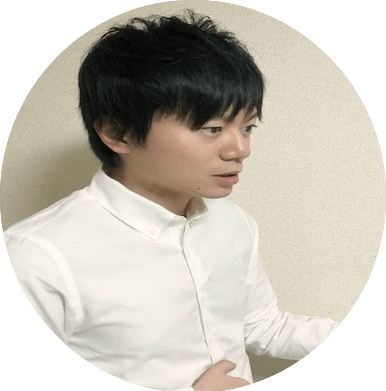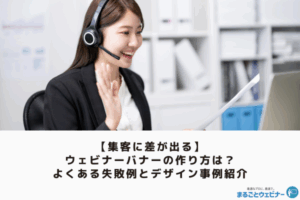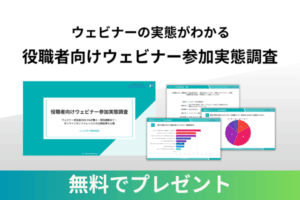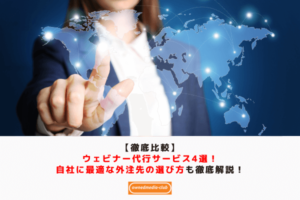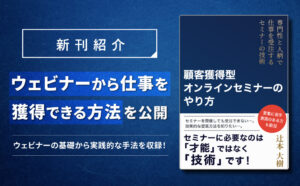共催ウェビナー(コラボウェビナー)とは?開催者側のメリット・デメリットをまとめてみた。

どうも。「まるごとウェビナー」の運営者、 辻本(YouTubeはこちら)です。
弊社はウェビナー運用を得意とする支援企業です。ウェビナーからのリード獲得、顧客獲得にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。(お問い合わせはこちら)
「共催ウェビナー」をご存知でしょうか?
「共催ウェビナー」とは、Web上でパートナーと一緒に開催するセミナーのことです。「コラボウェビナー」や「コラボオンラインセミナー」とも呼ばれます。
今回は、共催ウェビナー(コラボウェビナー)の概要および主催者側のメリット・デメリットについて記載したいと思います。
実際、僕自身、オンラインセミナーを500回以上開催してきました。(詳しい実績はこちら)
もちろん、共催ウェビナー(コラボウェビナー)も開催してきました。自分が感じたメリット・デメリットを忌憚なくまとめてみます。ぜひご参考にしていただければと思います。
本記事で学ぶ内容
- 共催ウェビナー(コラボウェビナー)の概要がわかる。
- 共催ウェビナー(コラボウェビナー)を開催するメリットがわかる。
- 共催ウェビナー(コラボウェビナー)を開催するデメリットがわかる。
・どこから手をつければよいか、具体的なやり方が分からない
・どんなテーマや企画であれば、見込み顧客の興味を引けるのか判断がつかない
・資料作成や集客準備に時間がかかり、本来の業務に支障が出てしまう
昨今、多くの企業がウェビナーを使ったリード獲得や顧客獲得に力を入れていますが、集客に成功し、問い合わせや売上に繋げるには、高度な知見が必要になります。
まるごとウェビナーは、2020年以降のオンライン化の波にいち早く対応し、累計1,200人以上の方々にご参加いただきました。そこで得られたノウハウをもとに、書籍『顧客獲得型オンラインセミナーのやり方』を出版し、さまざまな企業に再現性のあるウェビナー支援を行ってます。
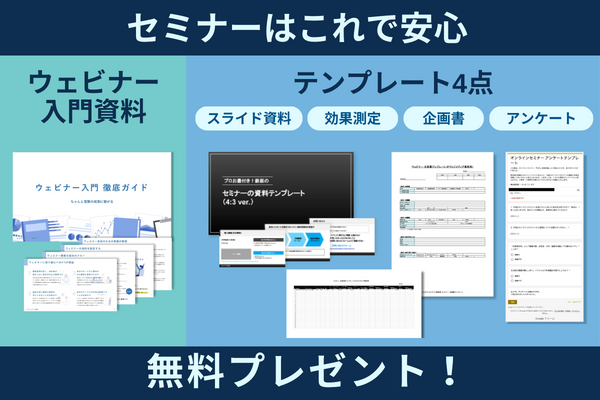
もし現状、ウェビナーに課題や伸び悩みがある場合は、まずは「ウェビナー成功のための5点セット」を無料ダウンロードしてください。
\ テンプレートも公開中! /
共催ウェビナー(コラボウェビナー)とは?
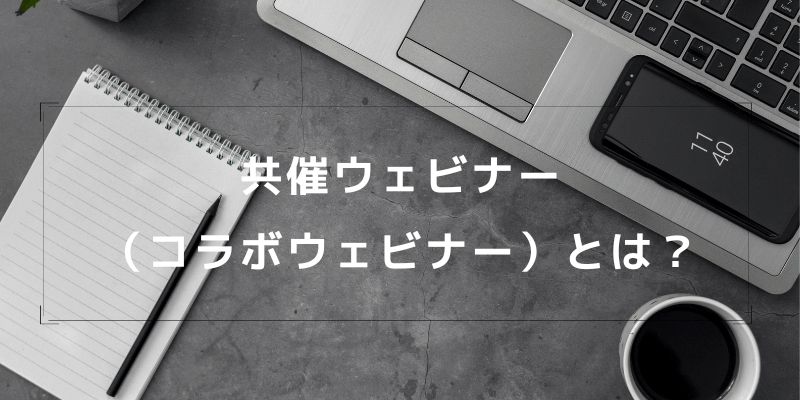
「共催ウェビナー」とは、オンライン上でパートナーと一緒に開催するセミナーのことです。「コラボウェビナー」や「コラボオンラインセミナー」とも呼ばれます。
Zoom・Microsoft teams・Google Meetsなどオンラインツールを使用して開催するため、場所に限定されずに運営することができます。
daiが開催した共催ウェビナー(コラボウェビナー)の実例
実際、daiが開催した共催ウェビナー(コラボウェビナー)の実例は下記の通りになります。様々な方々とコラボオンラインセミナーを開催してみました。
- 2021.10 死なない起業!? 「身の丈起業」から始めようコラボウェビナーを実施【実績はこちら】
- 2021.10 会社に頼らず生きるためのスペシャルトークライブ with.木村 悠氏(元ボクシング世界チャンピオン)【オンライントークライブ総括】【実績はこちら】
- 2021.11 ビジネスを加速させる!! スキルシェアサービスの勝ち方(ストアカ・aini) コラボウェビナーを実施【実績はこちら】
- 2021.11 受託商品から自社商品へ!! アクリル升(マスマス)の製造・販売秘話 コラボウェビナーを実施【実績はこちら】
- 2022.2 【現役POLAのオーナーとコラボセミナー】 女性が羨む肌に!! 自宅で手軽にできる。男性の肌スキンケア入門 コラボウェビナーを実施【実績はこちら】
- 2022.6 【個人事業主・小規模法人向け】初めての補助金活用(with 鈴木社長)【実績はこちら】
共催ウェビナー(コラボウェビナー)を開催する開催者側のメリットとは
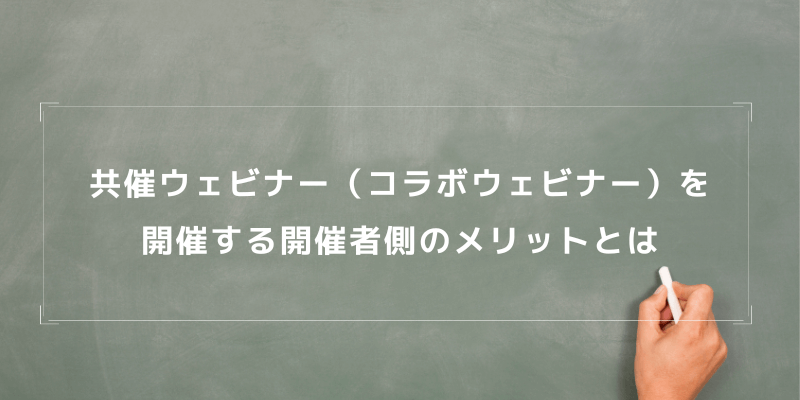
まずは、共催ウェビナー(コラボウェビナー)を開催する開催者側のメリットは、下記の通りになります。
- 双方の顧客名簿にアプローチできる。
- 双方で告知するため、認知効果が極めて高い。
- 集客目標に責任を持って活動するため、コミットしやすい。
- 有益なコンテンツを提供できる。
- 運営コストが低く、気軽に開催できる。
双方の顧客名簿にアプローチできる。
共催ウェビナー(コラボウェビナー)を開催するメリットの一つ目は、双方の顧客名簿にアプローチできることです。
WEB集客の場合、一般的にメルマガまたはLINEで顧客名簿を管理されていますが、自社ウェビナーでアプローチできる顧客名簿は自社が所有している名簿のみになります。一方、共催ウェビナー(コラボウェビナー)の場合、共催先(コラボ相手)の顧客名簿にも共催先のメルマガまたはLINEを通じてアプローチできるため、普段、自社だけではリーチしなかったお客さまが参加してくれる可能性があります。
双方で告知するため、認知効果が極めて高い。
共催ウェビナー(コラボウェビナー)を開催するメリットの二つ目は、双方で集客するため、集客効果が極めて高いことです。
自社開催のウェビナーの場合、全ての認知は自社の発信量のみなりますが、共催ウェビナー(コラボウェビナー)の場合、共催先(コラボ相手)も発信することによって発信量が2倍になります。(実際は、フォロー、リツイートなどのSNSを効果的に利用すれば2倍以上になります)
そのため、認知効果は自社開催の時に比べて効果的です。
集客目標に責任を持って活動するため、コミットしやすい。
共催ウェビナー(コラボウェビナー)を開催するメリットの三つ目は、それぞれ集客目標に責任を持ってコミットしやすいことです。
自社開催のウェビナーの場合、集客できなくても自社の責任です。一方、共催ウェビナー(コラボウェビナー)の場合、お互いが双方のメンツを立てる必要があります。「集客が全くできませんでした」というのは、共催先(コラボ相手)の方に失礼です。
そのため、お互い真剣に集客します。その最後まで諦めない気持ちが原動力となり、さらに成長させるきっかけになります。
 daiki tsujimoto
daiki tsujimoto私自身、共催ウェビナーを開催する場合、共催先と最低目標人数を握ります。例えば、「それぞれ3名を目標に集客していきましょう」、と最低目標人数を決めた上で双方告知していきます。
もちろん、集客できる、集客できないはあくまで結果でコントロールしづらいですが、一生懸命に試行錯誤しながら告知して、目標人数を達成させにいきます。その経験が今後の糧になりますよ^^
有益なコンテンツを提供できる。
共催ウェビナー(コラボウェビナー)を開催するメリットの四つ目は、有益なコンテンツを提供できることです。
双方にとってシナジーのある共催ウェビナーの場合、お客様のその領域を求めているケースが多いため、より有益なコンテンツを提供することができます。例えば、自社がブログ集客のテーマに開催し、共催先(コラボ相手)がグーグルアナリティクスのテーマに開催すると、ブログに興味のある人にとってより良い情報を提供することができます。
運営コストが低く、気軽に開催できる。
共催ウェビナー(コラボウェビナー)を開催するメリットの五つ目は、運営コストが低く、気軽に開催できることです。
リアルの共催セミナーであれば、会場を借りて運営するため会場費用がかかります。また、その会場までの交通費もかかります。一方、共催ウェビナー(コラボウェビナー)の場合、交通費、会場費用がかかりません。非常に画期的ですね。



コロナウィルスの影響により、オンラインセミナーが活発になりました。リアルではなく、オンラインセミナーを受講するのが当たり前になったことから、物理的な距離の障壁がなくなり、地方在住の方・海外在住の方の受講が活発になりました。次のフェイズとして、より効率よく集客するため共催ウェビナー(コラボウェビナー)を企業・講師・先生方に活用されています。
共催ウェビナー(コラボウェビナー)を開催する開催者側のデメリットとは
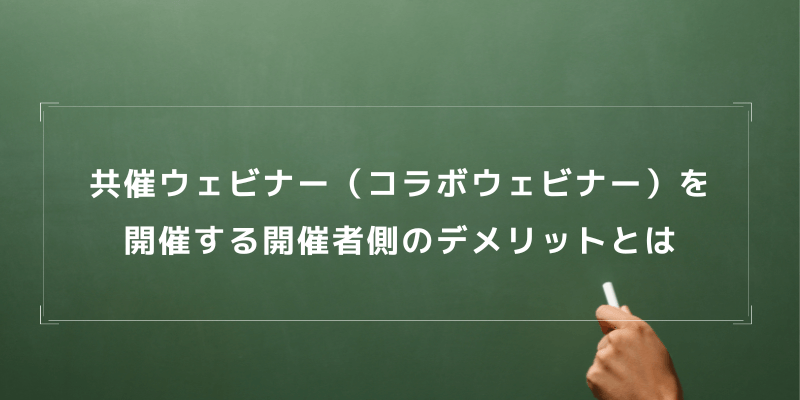
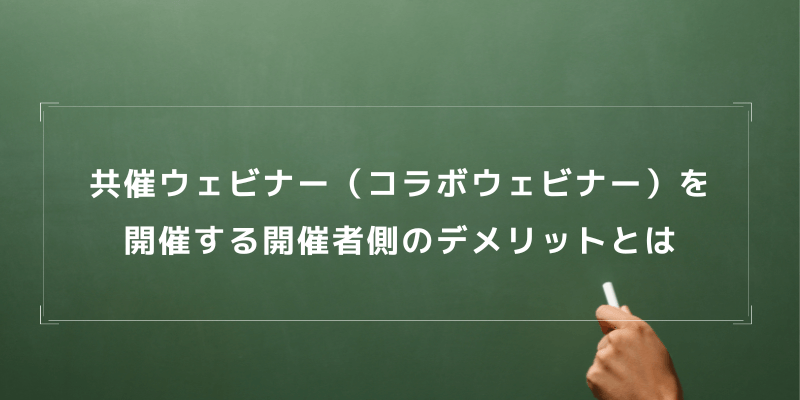
次に、共催ウェビナー(コラボウェビナー)を開催する開催者側のデメリットは、下記の通りになります。
- 共催先(コラボ相手)との打ち合わせが必要で作業工数が増える。
- シナジーのある共催先(コラボ相手)を見つけるのはやや難しい。
- 身体性を有する実技の共催ウェビナーは向いていない。
共催先(コラボ相手)との打ち合わせが必要で作業工数が増える。
共催ウェビナー(コラボウェビナー)を開催するデメリットの一つ目は、共催先(コラボ相手)との打ち合わせが必要で作業工数が増えることです。
自社開催のウェビナーの場合、自社内でやりとりは完結します。一方、共催ウェビナー(コラボウェビナー)の場合、企画・集客・運営・アフターフォローなど共催先(コラボ相手)と打ち合わせする必要があります。さすがにぶつけ本番で開催できないからです。そのため、打ち合わせなどの作業工数が増えてしまいます。
シナジーのある共催先(コラボ相手)を見つけるのはやや難しい。
共催ウェビナー(コラボウェビナー)を開催するデメリットの二つ目は、シナジーのある共催先(コラボ相手)を見つけるのはやや難しいことです。
自社の事業と関連性のある、かつコミュニケーション能力の高い共催先(コラボ相手)を見つけるのは難易度が高いのは事実です。探すコツとしておすすめは、身近な人に声をかけることをお勧めします。全く知らない人といきなり共催ウェビナー(コラボウェビナー)を開催するのはハードルがすごく高いからです。



私自身、共催ウェビナー(コラボウェビナー)は自分のお客さまをメインにお誘いしております。たまに外注先様にお願いすることもありますが、どちらにせよ、ビジネスで日頃からお世話になっている方と開催しています。
身体性を有する実技がある共催ウェビナーは向いていない。
共催ウェビナー(コラボウェビナー)を開催するデメリットの三つ目は、身体性を有する実技の共催ウェビナーは向いていないことです。
身体性を有する実技とは、例えば、サッカー・水泳・運転・手術などが挙げられます。実技を行うことでしか上手くならないものです。ただし、サッカーで言えば、サッカーの戦術、マネジメントなどは向いていますが、リフティング、シュート、ドリブルなどは実際、実演して確かめてほしいですよね。



ただ、私自身、ヨガに関してはオンラインで3年以上受講しております。身体性を有する実技であるもののジムに通うのが億劫だったり、女性が多くて通うのも気が引けて、、、オンラインヨガを受講しています。ケースバイケースですが、オンラインでも身体性を有する実技を提供できるものもあります。
【追記】YouTubeに「共催ウェビナーを開催するメリット・デメリット」を撮影しました
YouTubeに「共催ウェビナーを開催するメリット・デメリット」を撮影しました。良かったらご確認ください。
最後に
今回は、共催ウェビナー(コラボウェビナー)の概要および主催者側のメリット・デメリットについて記載しました。
弊社では、ウェビナーの企画・集客・運営・アフターフォローまでまるっと支援する、「まるごとウェビナー サポートプラン」を提供しています。ウェビナーからのリード獲得や顧客獲得にお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
また、自社保有の顧客名簿(メールアドレス)を持っていない方には「封書DMを活用したまるごとウェビナー サポートプラン」がおすすめです。封筒に入れたウェビナー案内チラシをターゲット企業に直接郵送し、ウェビナーへの参加を促進する新しいサービスです。従来のメルマガリストがなくても見込み客に直接アプローチできるため、新規顧客開拓やリード獲得にお困りの方に最適です。
ここがポイント